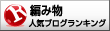袋編みの前立てを編む準備 その1「拾い目の数(の目安)と前立ての幅を決める」

前が開きボタンで閉じるカーディガンやベストを編むときは、身ごろに沿った前立てを編む必要があります。この前立てというのが実はとても難しくて(個人の感想です)、初めてやったときはかなり苦戦しました。一番の苦戦ポイントは拾い目。拾い目の数を決めるにも計算をしなければならず、私の場合は、計算していざ拾い始めてもなかなか辻褄が合わずに何度も何度もやり直しが必要で、編めばたった数段のゴム編みですが、ものすごく集中して丸一日取り掛かっていても、片方の前立てが出来上がるまでに一日以上かかり、ヘトヘトになってしまいました。それほど、私には難しかったのです。
あるとき、これなら簡単にできるかもしれない、と思った前立ての編み方を二つ知りました。そのうちの一つが、身ごろから首周りまでの前立て(というか縁?)の段数分を袋編みして縫いつけていく方法で、もう一つは、前立てを袋編みしながら編み付けていく方法でした。拾い目の数を事前に把握しておいた方がよいのはどちらもそうですが、ゴム編みの前立てのように、いくつか段を飛ばして拾い目をしなくてもいいので、これに関する煩雑な計算をしなくても良いのが、とても魅力的に感じました。
結果的にはどちらも同じ見栄えになることが分かっていたので、さまざまなことを考えて、いま編んでいる前開きベストのSienaでは後者の方法をやってみることにしました。
この方法は今回初めて取りかかることになるので、工程を簡単に書き出しておこうと思います。
袋編みの前立て Button placketsを編む準備
前立てを編む前に、まず最初にすることは、身ごろと首の後ろの縁から目を拾っていくことです。『ゴム編みの前立て』(日本語での正式名称が分からないので、ここではこう呼びます)だと、ゴム編みの伸縮性を考えて、適度に目を拾わない段があり、これを等間隔で行うため、それの計算をしなければならないという結構な手間がありますが、袋編みの前立ての場合はすべての段から目を拾えばいいので、こういった難しさはありません。
目を拾い始める前に、身ごろの段数や首の後ろの目数(Sienaの場合は前身ごろのVネックの段数も)を事前に把握しておくと、拾い目の目安ができるので、より作業がやりやすくなると思います。それぞれを編んでいるときに数えておくのが一番良いとは思いますが、私はそれをやらなかったので(なぜやらなかった……)、パターンに書かれているテキストから、それぞれの部分の段数を計算してまとめました。私が編んだSienaは下記のようになりました。
・裾 10目×2
・身ごろ(直線部分) 86目×2
・身ごろ(Vネック部分) 63目×2
・首の後ろ左右のカーブ 10目×2
・首の後ろ 34目
Vネックが終わったところに印を付け(Sienaはトップダウン)、身ごろを直線部分とVネック部分に分けておいてから、目を拾い始めました。

ほぼ目安通りに目を拾えたのですが、なぜだか左前身ごろの直線部分の目数が合わなかったので(右より2目少ない)、二三度最初から目を拾い直したのですが、それでもダメでした。ゴム編みの前立てとは違って、袋編みの前立ては左右で目数を必ず合わせた方が良いわけでもないので(ここが、袋編みの前立ての最大の利点かも)、もし編んでいるときに辻褄が合えばよし、合わなくても見た目にはまったく影響がないだろうと考え、ここはひとまずそのままにしておいて、前立ての袋編みを始めることにしました。

袋編みの前立ては、PetiteKnitのChampagne Cardiganの編み方で紹介されている動画『Champagne Cardigan – dobbeltstrikket knapstolpe』(動画製作:Kimmie Munkholm)を参考にしています。
さて、編み始める前に気を付けたのが、前立ての幅。
Sienaでは、別編みの前立てを作り目14で編むと書かれていました。ちなみに、PetiteKnitのChampagne Cardiganも14+拾い目とK2tog tblするための1目となっています。つまり、どちらもほぼ同じ幅。最初に14目と見たときは、これだと幅が広すぎなのではないかと思ったのです。
ということで、編み比べてみることにしました。上が14+1目、下が10+1目です。


裾のゴム編みが10段だったので、その高さとほぼ同じ幅である10+1目の方が全体的にバランスが取れていて見た目が良いような気がしたので、こちらの目数で編むことに決めました。