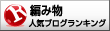ヒールフラップとガセットのかかとを同時編みでうまく編むには

昨日の記事で書いたヒールフラップとガセットのかかとを同時編みするのに、あまり深く考えずにテキトーにやっていましたが、やはり行き着く先は目のかけ変えだとハッキリしたので、もっと効率の良い方法を考えてみることにしました。誰だって簡単に思いつくことだろうし今更感がありますが、自分にとっての発見だったので書き残しておくことにします。
前回の投稿のやり方だと、ガセットでの減らし目の位置が、普段とは違う場所になってしまうため、間違いが頻発しそうだと感じました。ならばやはり、片方ずつ編むときと同じように、針1には拾い目を含むかかとの目だけを、針2には甲の目だけがかかっている状態にしたい。その方が間違いもなく少なく編めるハズ。
針に目がそう分けられるように考えたのが下記のやり方です。
必要な道具は、編んでいるのに使っている輪針だけでもできる方法はありますが(後述)、今回私がやったのは、同じサイズの別の針1本を使った方法です。
ヒールフラップを編み終えたら、表に返すと下記の図のようになります。


ガセットに入る前にフラップの両脇から目を拾うことになりますが、ここでどう編んでいくのかがカギになります。この図を使って説明すると、編む順番は次のようになります。
[1段目]
a1 → b1(拾い目) → a2 → b2(拾い目) → c2 → d2(別針で拾い目) → c1 → d1
[2段目]
a1 → b1 → d2(別針で拾った目を輪針の右針にかける) → a2 → b2 → c2 → c1 → d1
これで、どちらのくつ下も、かかと側(abd辺)と甲側(c辺)とで目が分かれて針にかかっていることになっているはずです(説明が難しい……)。
次の写真は、(針のかかり方がおかしいですが)一番最初のa1を編む前の段階です。

a1を編み、b1(拾い目)を編んだところ。

a1 → b1(拾い目) → a2 → b2(拾い目) → c2 → d2(別針で拾い目)を編んだところ。

続けてc1を編み、d1で拾い目をして、2段目のa1を編み終えたところ。ここで別針で拾った目を輪針の右針にかけて、続きのa2 → b2……と続けます。

これでかかと側と甲側に目を分けられました。

d2を拾うのに別針を使わずに編むなら、d2の拾い目を2段目で行う方法もあります。そのさいの編む順番は次のようになります。
[1段目]
a1 → b1(拾い目) → a2 → b2(拾い目) → c2 → c1 → d1
[2段目]
a1 → b1 → d2(拾い目) → a2 → b2 → c2 → c1 → d1
今回使っているのが80 cmケーブルの輪針だったため、途中ケーブルがちょっと短く感じやりづらさがあったので、私は別針を使って1段目でd2の拾い目をしましたが、たぶん別針を使わなくても上の方法で編めると思います。今度自分でも試してみようと思います。
いままでヒールフラップとガセットのかかとを編むさいは、それまで同時に編んでいても、片方を別針に休ませたりして、片方ずつを編んでガセットが終わったら、再び同じ針にかけて編む……という方法を取っていましたが、今後はこれで分ける必要もなく、かかとも同時編みできるようになりました。よしっ。
![]()