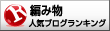袋編みの前立てを編む準備 その2「ボタンホールの数と位置、大きさを決める」

前回『袋編みの前立てを編む準備 その1「拾い目の数(の目安)と前立ての幅を決める」』の続きです。
今回は前立てに作るボタンホールについていろいろと決めていきます。
カーディガンや前開きベストの丈の長さにもよって変わってきますが、ボタンホールの数と位置と大きさを考えるのはほぼ同時だと思います。それでも、おそらくこの三つで一番最初に考えるのは、ボタンホールの大きさかもしれません。
付けたいボタンの大きさによって変わってくるのは当然で、前立てを編んだとき、1目の縦の長さを基準に考えます。私の手の場合、1目の縦の長さが5 mm(使用糸はAran)だったので、ボタンホールを1.5 cmにするか2 cmにするかちょっと迷って後者としました。つまり縦4目のボタンホールとなります。
ボタンホールの大きさが決まったら、次はボタンホールの数と位置。Sienaの場合、パターンにあるサンプル写真がボタン五つだったので、同じにすると決めていました。あとは位置です。Vネック用の増し目が終わって増減なしで編んでいく身ごろの目数と位置をうまい具合に合わせて、どこにボタンホールを編むかを決めます。これについては、一応軽く計算しましたが、結構大雑把に決めました。

で、ようやく編んで行くことになります。
袋編みの前立ての編み方は、前回の投稿にも書きましたが、次の動画『Champagne Cardigan – dobbeltstrikket knapstolpe』(動画製作:Kimmie Munkholm)を参考にしています。
そして、ボタンホールは『Champagne Cardigan – PetiteKnits Knaphuller i dobbeltstrik』(動画製作:Kimmie Munkholm)を参考にしました。なお、Knaphuller i dobbeltstrikは、「ダブルニット(袋編み)のボタンホール」とかそんな意味のようです。
で、編んでみたらこんな感じになりました。

上の動画では、前立ての最後の目と拾い目を2目一度にするさいK2tog tbl(Knit two together through the back loop)で編んでいますが、それだと重なる上の目がねじり目になります。実はねじり目でもあんまり目立たないのでK2tog tblでもいいのですが、ひと手間加えて、前立て最後の目を表目を編むように右針を入れて目を移し、それを左針に戻してから右上2目一度すると良いと思います。
もしくは、前立て最後の目と拾い目を右上2目一度して裏返したら、最初の目(つまり表で右上2目一度してできた目)を表目を編むように右針を入れて目を移しておくと、表側で行う工程が減るので、個人的にはこちらがオススメです。
こうすると表に見える目はねじり目になりません。ただし、2目一度の下の目(身ごろ縁の拾い目)はねじり目になりますが、その方が拾い目が締まるので、私はそうしています。
![]()