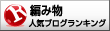脇の下の作り目について ~Magnolia

ここのところRiddariの記事が続いていましたが、自分にとっての難関突破(一段で3色を使って編む)ができたので、今回はMagnoliaに取り掛かりました。
以前の投稿では、まだ数度の増し目が残っていましたが、それも終わり、身ごろから袖を分ける段階まできました。
以前の投稿の写真を見ると(下記)、まだ増し目を始めたばかり、という感じですね。
ほかのトップダウン Top-Downセーターでも同じことが言えますが、このMagnoliaでも身ごろから袖を分けるとき、袖になるところは目を休めて、脇の部分でいくつかの作り目をします。
ここでの作り目、セーターを編む方々はどうしてらっしゃるのだろうといつも思います。
私の場合ですが、簡単だからという理由だけで、いつも巻き増し目 Backward Loopでやっていました。巻き増し目(というより、ここでは巻き作り目)は、作った輪をねじりながら針に引っ掛ける作り目で、その場ですぐに目を作り出せる上にとても簡単な方法です。下の写真は、巻き増し目で作り目をしたものです。

巻き増し目のやり方は、動画で分かりやすく説明されています。
しかし、今回は思うところがあって、English Style Cast on(← これの和名ってあるんでしょうか?)にしてみました。下の写真は、English Style Cast onで作り目をしたものです。

増し目をこのEnglish Styleでするのは、一般的なやり方かは分かりませんが、私はたまに使っていました。巻き増し目同様、その場ですぐに目が作り出せるのが魅力です。
私はEnglish Style Cast onを、ドイツに住んでいたころに、ニットデザイナーの三國万里子さんの動画(ほぼ日)で初めて知りました。
この方法は、指でかける作り目(日本では、英語でいうLong Tail Cast onと呼ばれる方法が一般的)と比べると、たくさんの目数を作り目しなければならないときに、重宝しています。指でかける作り目は、どこから始めるのかをさまざま方法でその場所を見つけてから作り始めます(そうしないと、最後の最後で糸が足りなくなってもう一度やり直しになります。そのため、作り目から心が折れる場合も多々……)。ドイツ式作り目 German Cast Onや指でかける作り目 Long Tail Cast Onをするさい、どれくらいの長さを準備すればいいのか、その長さの測り方を下記記事で紹介しています。
しかし、このEnglish Styleは、そんなことも気にせずに作り目ができるので、使い分けるようにしています。それでも、一番最初の作り目は、伸縮性を優先してしまい、指でかける作り目のGerman Cast onを使いがちですが。
ちなみに、最初はこのやり方を、なぜEnglish Styleと呼ぶのかが分かりませんでしたが、私が所属しているニッティング・グループ Knitting Groupを主催している方を始めとする年配のイギリス人たちは、この方法(もしくはこれに近いやり方)で作り目をしていて、これがイギリスのやり方なのだと言われて、その名の由来が分かったのでした。

ということで、袖分けができました。
いつもなら身ごろを数段編んですぐに袖を編み始めてしまうのですが、今回は裾にお楽しみの模様編みがあるので、このまま身ごろを編んで行こうと思っています。